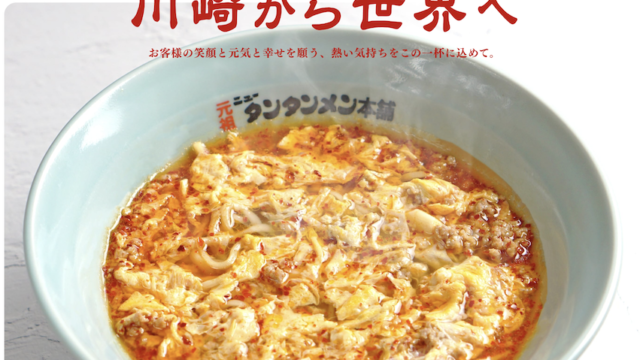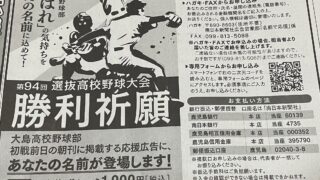692)_氷瀑が見える日本二百名山の大崩山へ(°▽°)/ その2
2022年1月15日に登頂した大崩山の報告です!
その1として、下記でご報告しております。
その続きですが、9時51分に登山開始です。
ルートの標準タイムは7時間なので、そのまま足すと休憩なしで17時です。
初めてのコースで、冬で、日が暮れた状態では危険です。
急いでコースを進むことにします。
大崩山荘までは、祝子川(ほうりがわ)に沿った緩やかな山道を歩きます。
15分ほどで、山荘に到着です。

無人の避難小屋なのかどうか分かりませんが、立ち寄ることなくスルーして先を急ぎます。
そして、分岐です。

左方向を示す坊主尾根は帰り道の予定です。
右ルートを進みます。
しばらくは落ち葉が深い登山道を歩きます。

そして、祝子川の渡渉です。
手前のピンクリボンから、川向こうのピンクリボンを目指して河原を進みます。

水が溜まっているところは氷が張っています。
割ってみるとかなりの厚さです。
1cm以上の厚みです。

この日の靴も破れたトレランシーズです。
雪が少しあったので、テーピングを巻くと滑りやすいかなと思い、あえて破れたままです。

幸い水量も少なく水に濡れることなく渡渉完了です。
沢の奥には、岩肌が見えています。

渡渉を終えて、山に入ると雪が出てきました。
深い雪ではありませんが、しっかりあります。
少しルートを外れたところに眺望が望めるポイントがありましたので、そちらに向かいます。

眺望ポイントからドーム状の岩が見えます。
名前がついている様な立派な岩です。


名前のとおり大きく崩れそうな山を実感する景色ですが、これから先はもっと崩れそうな岩がどんどん出てくることは知るよしもありません。
岩と雪が混じる急斜面を登ると、袖ダキ展望所です。

そこには、まさに大崩山という景色がありました。
どうぞ。。

展望台からの光景はものすごい迫力です。
本当に今でも崩れそうな岩に圧倒されます。

さらに進んだ岩のテラスで、人の姿がありました。
結局、この日唯一お会いした登山者Aさんです。
ブログに載せることまで了解してもらっていないので、顔は隠しました。

熊本から約3時間掛けて来られたとのことで、私と同じような感じです。
初めての大崩山とのことで、それも共通点がありましたが、YouTubeでかなりこのルートの動画を見られているようで、おおよそ頭に入っているとのことでした。
便利な世の中です。
北を見ると九重連山と思われるお山の姿も見えてきましたよ。。。

そして本日のメインである氷瀑の姿です。
まずは、こちらから↓↓

あれが滝なの??
拡大します。

さらに拡大です。
確かに氷です。

大きさが分からないくらいですが、おそらく相当デカイはずです。
氷瀑の下から見たらモノスゴイ迫力だと思います。
ゆっくりと眺望を楽しむ時間的な余裕もないため、更に先に進みます。
しばらく登って、稜線に出ると、帰り道の坊主尾根との分岐に到着です。
ここからしばらくはなだらかな道となります。

この日の天気は晴れの予報でしたが、少し雲が多かったです。
それでも風が無かったので、寒く感じることは無かったです。

山頂の手前で、360度の視界が広がるポイントがあります。
やはりYouTube動画で予習してきた方がいいのかもしれませんが、遠くに見える山々が同定できません。
おそらく、祖母山、傾山あたりと思われます。


最後の上りには先客の足跡がありました。
鹿さんなのか、カモシカさんなのか分かりませんが、人間ではないことは間違い無いです。

2022年1月15日、12時50分、大崩山登頂です!
いのとも、52歳。
12時50分、標高1644mの大崩山山頂に到着です。
ちょうど3時間です。

久々の自撮り写真です。
写真もそこそこに、昼食です。
初登頂で、岩と雪の難コース。
疲れました。
お腹もペコペコです。
お湯を沸かして、カップヌードルとフォカッチャを頂きます。
山頂独り占めです。

短い休憩で、山頂を後にします。
遅くなると暗くなってしまいそうです。
途中、九重連山と思われるお山の姿が綺麗に見えましたよ!

実は実は下りのコースを予定していた坊主尾根がナカナカの曲者の様です。
下り途中に熊本のAさんと再会するのですが、下りコースはどのコースで下るのか質問されました。
私は、同じコースをピストンするよりは違うコースを歩いた方がいいという簡単な気持ちでしたが、坊主尾根は手強い相手でしたよ。
その様子は次回ということで、宜しくお願い致します。
つづく。。。